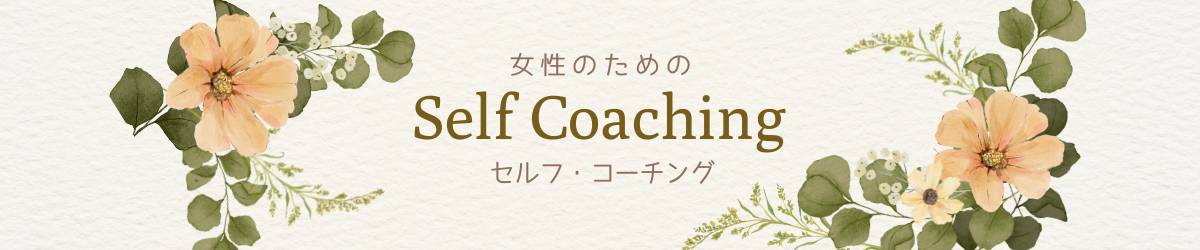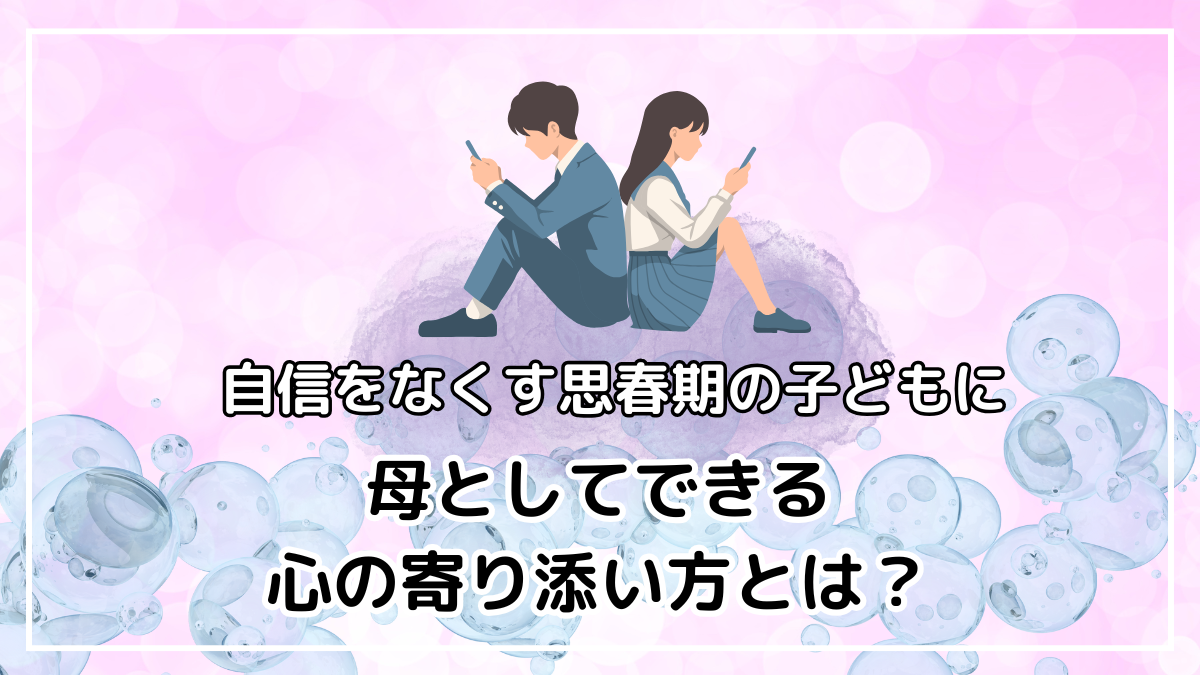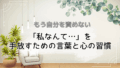「下の子が最近、何をするにも無気力に見える。自信がないのかな・・・」
先日久しぶりに会った友人が、ぽつりと話してくれました。
小学校高学年のお子さんの話でした。
彼女の話を聞きながら、私は幾度となく頷いていました。
私も以前、下の子が何をするにも自信を持てずにいる姿を見て、どう関わればいいのか悩んでいたことがあったからです。
「年齢的なものかな」「そのうち変わるよね」と楽観的に構えていては埋まらない溝。
彼女の悩みには、私自身が見過ごしてきたことと重なる部分がたくさんあり、他人事には思えませんでした。
親の意図と、子どもの受け止め方のすれ違い
彼女の話の中で、特に印象に残ったのは、
「上の子のことでいっぱいいっぱいだったんだと思う。下の子は手がかからないし、ちゃんとしてるように見えて、ついひとりでできるよねって思ってしまっていたんだと思う。」
という言葉でした。
この感覚、実はとても多くの親が経験しているのではないでしょうか。
親としては「信頼して任せている」つもりでも、子どもにとっては「自分は見てもらえていない」「上の子の方が大事なんだ」と感じてしまう。そしてそれが、「自分は価値のない存在かもしれない」という思い込みを生み、心の奥に静かに根を張っていくことがあります。
彼女の場合も、上の子の進路や学力をずっと気にかけてきた一方で、下の子のことは「大丈夫だろう」とどこかで後回しにしていたこと、4人家族の彼女は、上の子がお母さん、下の子はお父さんと分かれて分担することが多かった為、彼女自身が、下のお子さんと「一緒に」何かをする経験が極端に少なかったこと…
下の子は本当は寂しかったんじゃないのか、何かの小さなサインを見逃していたのではないか、今になってその影響が表れている気がしてならないと、涙を浮かべながら話してくれました。
子どもが発する「遠回しなSOS」
彼女の話には、母としての後悔と戸惑いが溢れていました。
思春期の子どもは、言葉で助けを求めるのがとても苦手です。
「べつに」「どうでもいい」「やってもムダ」
そんな言葉の裏にあるのは、本当は「気づいてほしい」「自分をちゃんと見ていてほしい」という切実な気持ちかもしれません。
友人の下の子も、最近は誘っても「いいや」と言うことが増え、人との関わりを避けがちになり、「自分はいい。」と言う言葉が口から出るたびに、母として胸が締め付けられると語ってくれました。
周囲から見れば「繊細な子」と表現されがちですが、親として見ると、その子は「人を信頼すること」そのものに迷いや不安を感じているように映っているのです。
「このまま大人になっても、人間関係でつまずくのではないか」
「自分を責め続ける癖が強くなってしまうのでは」
そんなお子さんへの心配が、お母さんの心に重くのしかかっているようでした。
心が閉じかけた子に、今からでもできる4つのこと
私自身、コーチングやカウンセリングの視点を学ぶ中で、「関係を修復する入り口」は、過去を責めることではなく、「今ここ」の関わり方にあると気づきました。
ここでは、彼女と共有した【4つのステップ】をご紹介します。
1. アクティブリスニングとは?|子どもの話を安心して聴く技法
遮らず、否定せず、最後まで「聴く」こと。
正しい答えやアドバイスを返そうとせず、「そう思ったんだね」「それは辛かったね」と、子どもの言葉をそのまま受け止めてみてください。
“ちゃんと聞いてもらえた”という感覚が、子どもの自己肯定感を支える土台になります。
話すことで気持ちを整理できる子どもも多く、自分の中にある不安や葛藤を言語化できるようになります。
やがて、「ママなら聞いてくれる」と思えるようになり、信頼関係が少しずつ築かれていくのです。
2. リフレーミング(視点の転換)|子どもの短所を“別の光”で照らしてみる
リフレーミングとは、「見方を変えることで、意味づけが変わる」心理的な技法です。
たとえば、
「うちの子は頑固で…」と思っていたけれど、
それは「自分の意見をしっかり持っている」という強さかもしれません。
「すぐに泣く子」は、「感受性が豊かで、他人の気持ちに寄り添える子」。
「飽きっぽい子」は、「好奇心が旺盛で、新しいことにどんどん目が向く子」。
親が先に“別の光”で子どもを照らしてあげると、子ども自身も「自分って悪くないかも」と思えるようになります。
短所を否定するのではなく、視点を変えて捉え直すこと。
それが、子どもの自己肯定感を育てる大きな一歩になります。
3. Iメッセージとは?|子どもを責めずに気持ちを伝える方法
「あなたは〜」ではなく、「私は〜」で気持ちを伝える方法。
例えば…
「あなたは冷たい」ではなく、「私は、返事がないと寂しく感じる」
この表現に切り替えることで、子どもは「責められている」のではなく、「大切にされている」と受け取るようになります。「自分のせいだ」と思いやすい子にとって、安心して感情を受け取れる関係の第一歩になります。
4. 小さなYESが信頼を育てる|親子関係の再構築ステップ
特別なことをしなくても、関係は温め直せます。
「一緒にお茶を飲まない?」「少しだけ話してみない?」
小さなYESが積み重なることで、「受け入れられている」「自分はここにいていいんだ」という実感が育ちます。
また、会話がない時間も、実は関係性を育てる大切なひとときです。
一緒にテレビを見たり、買い物に誘ってみたり、「特別なことをしない」時間を共有することが、心の距離を縮めるきっかけになります。
時間を共有することで親子の会話が自然と増え、気まずさや距離感が少しずつやわらいでくるのです。
後悔ではなく、「今ここ」から始めよう
「今までごめんね」「本当は、もっとちゃんと向き合いたかった」
そんな言葉を、親から子へ素直に伝えることは、決して弱さではありません。
むしろ、その誠実な姿勢こそが、子どもの心にまっすぐ届くのだと思います。
子どもを変えたいと願うなら、まずは親自身が「完璧じゃなくても大丈夫」と、自分をゆるすことから始めてみてください。
気づいた“今日”こそが、子どもとの関係を温め直す最初の一日になります。
心の距離は一日では縮まりません。けれど、小さな関わりの積み重ねが、「また通じ合えるかもしれない」という感覚を、少しずつ取り戻させてくれます。
過去の関わり方を責めるのではなく、「これからどう向き合っていくか」を選び直すこと。
その選択が、親子の未来を変える力になるはずです。
あなたの今日の関わりが、子どもの自己肯定感をそっと育てていくのです。
あなたに問いかけたいこと
「いつもそばにいるよ」
「あなたのこと、大切に思ってるよ」
それの想いは、子どもの心に届くかけがえのないギフトになります。
お母さんの言葉と行動で、その想いを届けていけますように。