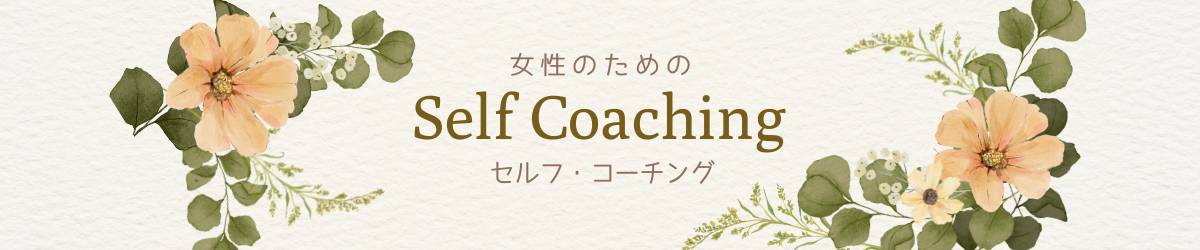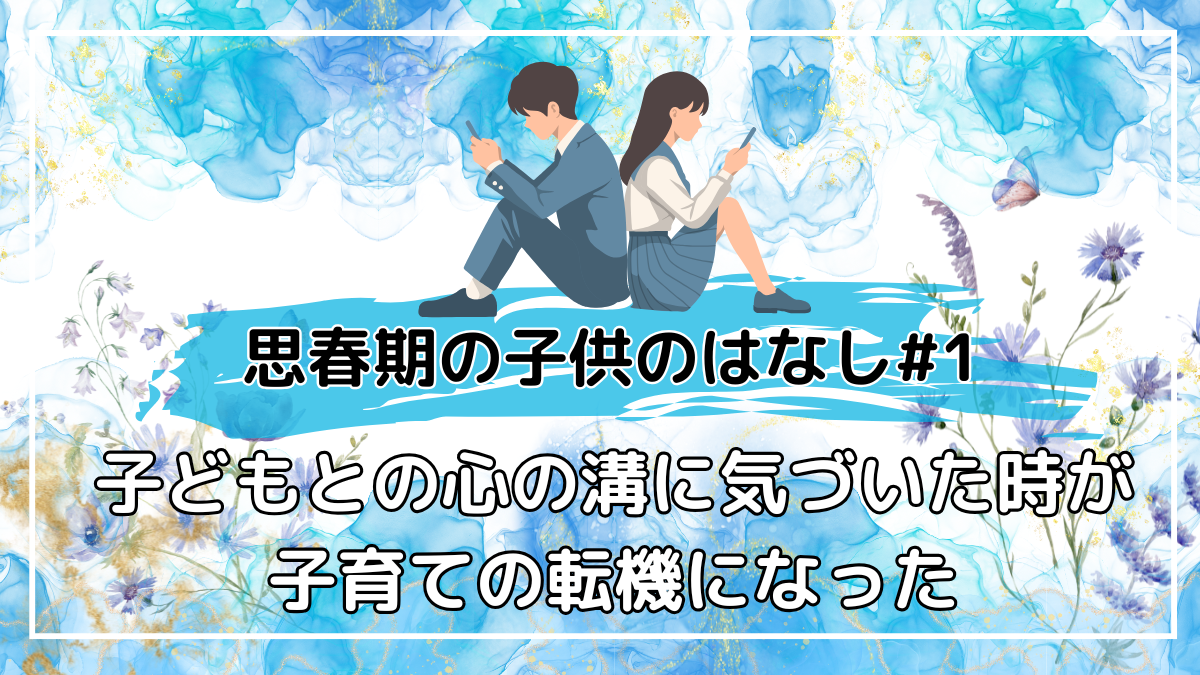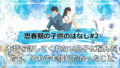✔️ 本記事は「子育てのモヤモヤ」シリーズの導入記事です。
この記事では、私の実体験を率直に綴っています。
母として、ひとりの人間として、子どもと向き合う中で感じた戸惑いや後悔、そして気づきを、同じように悩んでいる方に向けて共有できたらと思います。
我が家の子どもたちがまだ小さかった頃、私は「ちゃんと育ってくれればそれでいい」と思いながら、日々ふりかかる出来事に必死で向き合っていました。
「私自身はどんな子育てをしたいのか」
「どんな親でありたいのか」
そんな想いが少しずつ芽生え始めたのは、長男が幼稚園に入った頃。離乳食も、習い事も、学校行事も──親としての“初めて”はすべて長男と一緒に経験しました。だからきっと、私の子育ての基準は無意識のうちに「長男」でできあがっていたのだと思います。
そんな母と兄の背中を見て育った次男に関しては、同じようにはいきませんでした。
実際のところ、次男は長男に比べて手がかからず、何でも器用にこなすように見える子でした。いえ、正確に言うなら「器用にこなしているように見せるのが上手な子」でした。小学校高学年に差し掛かるまでは、私は次男のことで悩んだ記憶がほとんどありません。兄の行事に連れまわし、友達関係も兄中心。そんな日常の中で、私は「この子は大丈夫」と、彼の心の声に目を向けることを後回しにしていたのかもしれません。
思春期が近づき、彼は次第に自分のことを話さなくなっていきました。人付き合いを避け、できていたこともやろうとしない。そんな姿に対して、私の中には「甘えなのではないか」と思う気持ちもあり、彼の変化を「背中を押してあげればいい」と、私だけの思いで動かそうとしていたのです。
結果として、その無理な“後押し”は、反抗という形で私に返ってきました。
今まで問題なくいっていた(と思っていた)次男との関係が崩れ始めた頃、私はようやく気づきました。
「私は母親として信頼されていないのかもしれない」
そう感じて、愕然としたのです。
「このタイミングで、次男としっかり向き合わなければ──だめになってしまう」
寄り添わずに背中を押し続ければ、子どもは「分かってもらえていない」と感じてしまいます。
信頼ではなく、孤独とプレッシャーを感じるのです。
その後、私は彼の気持ちを“引き出そう”と必死になりました。でもそれは、信頼ではなく“無理やり”だったのかもしれません。振り返れば、私自身の不安や焦りを、彼にぶつけていたに過ぎなかったのです。
このシリーズでは、そんな私自身の体験をもとに、
- 子どもが本音を話してくれないとき、親はどう受け止めればいいのか
- ネガティブな言葉ばかり使う子に、どう寄り添えばいいのか
- 自信がなく、学校に行きたがらない子と、どう向き合えばいいのか
といったテーマを取り上げ、私が学んだセルフコーチングの視点や心理学的な理解を交えながら子供との関係性にどう変化があったかを記録に越します。
私も悩んでいます。そして今も、毎日が模索の連続です。
それでも、同じように悩んでいるお母さんたちへ。
このシリーズが、少しでも気づきや安心感につながることを願っています。
【次回】本編記事①「本音を話してくれない12歳の息子──私は信頼されていないの?」